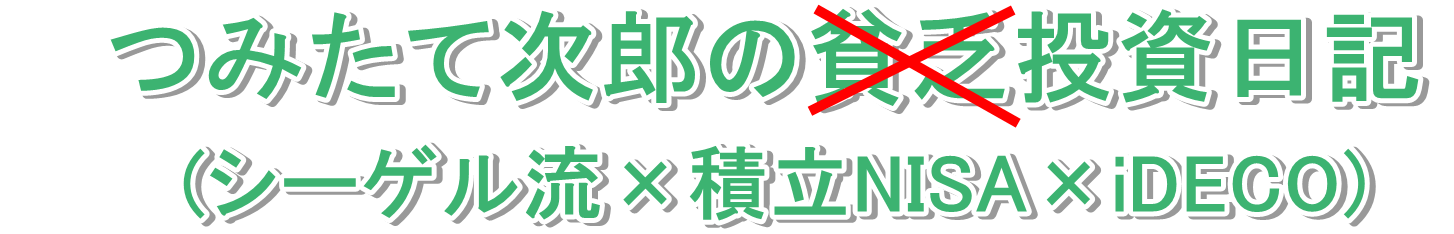生き残りS&P500の黄金銘柄
シーゲル二郎です。
米国市場を表すベンチマークとして現在最も有名なのは、S&Pグローバル(SPGI)傘下のスタンダード&プアーズが定める「S&P500」です。
S&P500は、米国を代表する大企業500社の浮動株調整後時価総額基準の平均で、米国市場の大半をカバーしています。
現在の500社体制が始まったのは、1957年からで、当時は時価総額でNY証券取引所全体のうち85%をカバーしていました。
業績などに応じて適宜入れ替えされており、当初の500社と現在の500社は大きく違っています。ジェレミー・シーゲル氏は著書にて1957年当時の500社のうち、現在も存続している企業の中で運用成績トップ20を発表しました。
| 当時会社名 | 現在会社名 | 利回り | セクター |
|---|---|---|---|
| フィリップモリス | アルトリア | 19.88% | 生活必需品 |
| アボット | アボット | 15.86% | ヘルスケア |
| クレーン | クレーン | 15.47% | 資本財 |
| メルク | メルク | 15.43% | ヘルスケア |
| ブリストール・マイヤーズ | ブリストル・マイヤーズ・スクイプ | 15.4% | ヘルスケア |
| ペプシ・コーラ | ペプシコ | 15.4% | 生活必需品 |
| スウィーツ・コーポレーション | トゥッツィー・ロール | 15.4% | 生活必需品 |
| コカ・コーラ | コカ・コーラ | 15.05% | 生活必需品 |
| コルゲート・パルモリーブ | コルゲート・パルモリーブ | 14.99% | 生活必需品 |
| アメリカン・タバコ | フォーチュン・ブランズ | 14.92% | 生活必需品 |
| HJハインツ | HJハインツ | 14.48% | 生活必需品 |
| ファイザー | ファイザー | 14.48% | ヘルスケア |
| マグロウヒル | マグロウヒル | 14.31% | 一般消費財 |
| シェリング | シェリング・ブラウ | 14.22% | ヘルスケア |
| WMリグレー | WMリグレーJr. | 14.15% | 生活必需品 |
| シェルンベルジェ | シュルンベルジェ | 14.06% | エネルギー |
| プロクター・アンド・ギャンブル | プロクター・アンド・ギャンブル | 14.05% | 生活必需品 |
| ハーシー | ハーシー | 14.02% | 生活必需品 |
| クローガー | クローガー | 14.01% | 生活必需品 |
| メルヴィル・シュー | CVS | 13.85% | 生活必需品 |
トップはご存知の通り、世界№1タバコメーカーのアルトリアです。現在は、フィリップモリス・インターナショナル(PM)とアルトリアグループ(MO)に分離しています。
上位20銘柄のうち、半分以上が生活必需品セクターになっています。生活必需品セクターは、米国株のセクター別長期リターンでも、ヘルスケアに次ぐ高リターンを生み出しています。
上記の結果から、生活必需品セクターに多く投資をする人が多くいます。
しかし、上記のデータを信じて投資をする場合、個別株ではなくセクターETF等を用いて投資する必要があります。
上記銘柄の多くは、平均PERは市場平均よりちょっと高いくらいだったが、EPS成長率が市場平均を大幅に超えていたという特徴があります。
つまり、平均よりちょっと上の成長しか期待されていなかったけど、実際は平均を大幅に超える業績だったということになります。
2017年6月30日現在、生活必需品セクターの利益成長率は平均を大きく下回っています。
| セクター(ティッカー) | 利益成長率 |
| 生活必需品(VDC) | 5.1% |
| S&P500(VOO) | 8.1% |
バンガードの人気ETFであるVDCとVOOから利益成長率を引っ張ってみました。利益成長率が自社株買いの影響を加味しているのか不明なので、もしかしたら差は縮むかもしれません。
ですが、それを踏まえても生活必需品セクター全体が市場平均以上の利益成長をするとは考えにくいです。特に米国株投資家が好んで選んでいるコカ・コーラ(KO)、ウォルマート(WMT)などであればなおさら市場平均を超えた成長をすることは難しいでしょう。
言い換えれば、既に巨大化してしまったこれらの企業は、市場平均を超える成長をすることが難しいのでこれからの黄金銘柄になる可能性は低いということです。
上記のような超大型企業に投資している人は、今後50年後の運用成績トップ20位になると思って投資している訳ではないと思います。
とはいえ、成長率とリターンそのものは比例しないので、ボラティリティを抑えつつリターンでも市場平均を超える可能性は十分高いです。
生活必需品セクター企業の中に未来の黄金銘柄が含まれている可能性は高いが、それは上記のような低成長な超大型株ではないということです。
末来の黄金銘柄に投資をしたいなら、素直にセクターETFを使うか、大手最弱から大手最強まで登りつめたけどずっと割安だったフィリップモリスのような、生活必需品バリューグロース株を自力で探すしかないということです。
参考記事「生活必需品セクターETF対決」
最後に、ジェレミー・シーゲル氏の著書「株式投資の未来」で記されていた内容で最後にしたいと思います。
生活必需品セクターの過去半世紀の成績が、一般消費財セクターを上回ろうとは、だれが予想しただろう。
配当貴族に投資している身としてアレですが、生活必需品セクターが今後も卓越したリターンをもたらすかどうかについては懐疑的です。
![]()
にほんブログ村
黄金は予想しないところから見つかる