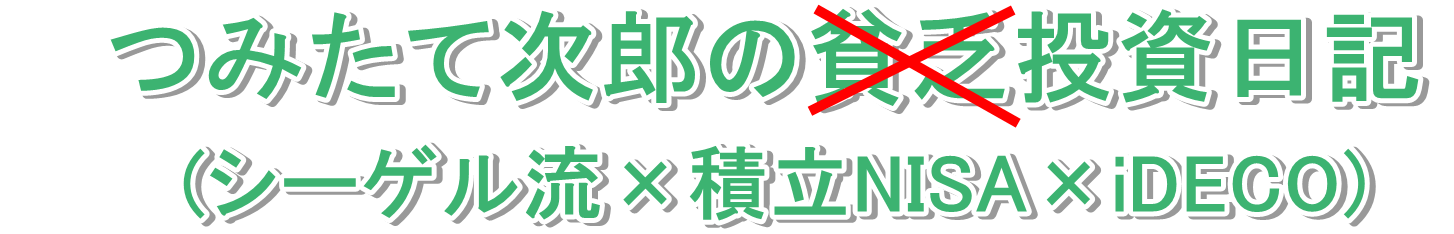【書評】株式投資の未来【バイブル】
つみたて次郎です。
久しぶりにジェレミー・シーゲル氏著「株式投資の未来(通称:赤本)」を読み返してみました。
 |
新品価格 |
![]()
当ブログでも度々登場していますが、元々のハンネが「シーゲル二郎」、現在もサブタイトルに「シーゲル流」と入れているにもかかわらず、本自体について書評を書いたことがなかったので今回記事にしてみました。
赤本はつみ次郎の投資哲学を大きく変えた1冊であり、バイブルとも呼べる存在です。
2019年最後の記事を締めくくるのに相応しいといえますね(自画自賛)
また、今回は赤本の中でもあまり語られることのない裏シーゲル(?)の部分を中心に考察していきたいと思いますので、赤本を読んだことのある方もそうでない方も、ゆっくり楽しんでいただければと思います。
大晦日にこのブログ読んでる時点で相当暇人ですからね
IBM vs スタンダードオイル
赤本の第1章は「成長の罠」となっており、これこそが赤本を読み解くカギとなるワードです。
高成長で期待の高い銘柄は高い値段で取引されやすく、結果としてリターンは冴えない物になりやすいという理屈です。
株式投資におけるリターンのほとんどは、この成長の罠という言葉で片付けれてしまいそうなほど汎用性が高く、普遍的な概念と言えます。
そんな成長の罠ですが、それを説明する例として、赤本ではインターナショナル・ビジネス・マシーンズ(IBM)とスタンダード・オイル・オブ・ニュージャージー(現在のXOM)の2銘柄を比較しながら考察されています。
1950~2003年における各銘柄の指標は以下のようになっています。
| IBM | 旧XOM | |
| 1株当たり売上 | 12.19% | 8.04% |
| 1株当たり配当 | 9.19% | 7.11% |
| 1株当たり利益 | 10.94% | 7.47% |
| セクター成長率 | 14.65% | -14.22% |
| 平均株価収益率 | 26.76倍 | 12.97倍 |
| 平均配当利回り | 2.18% | 5.19% |
| 株価上昇率 | 11.41% | 8.77% |
| トータルリターン | 13.83% | 14.42% |
参考文献「株式投資の未来」
エネルギーセクターは時代の流れから縮小し、株価成長率も冴えない…にもかかわらず、急成長を遂げたハイテクセクターのトップを走っていたIBMよりもトータルリターンが良かったというのが結論です。
IBMには高い成長が期待されていた結果、株価は割高になり、リターンを押し下げたという理屈です。
逆に、スタンダードオイル(旧XOM)は成長率も株価成長率もあまりよくなかった代わりに、期待が低かったので安く買付することができ、配当金再投資により加速的にリターンを押し上げたというハッピーエンドです。
…というのが赤本での趣旨なのですが、つみ次郎としてはなぜこの2銘柄を挙げたのか?という疑問があります。
というのも、最終的なトータルリターンの差はぜいぜい1%もなく、数字のインパクトに欠けます(半世紀の1%だから実際はものすごい差ではありますが)
また、さらに致命的なのが、同期間(1950~2003年)におけるS&P500のトータルリターンは11.44%であり、どちらの銘柄も大幅にアウトパフォームしているという点です。
なので、IBMが負け組・スタンダードオイルが勝ち組というよりは、IBMが超勝ち組・スタンダードオイルが超超勝ち組にしか見えないというのが、つみ次郎の感想です。
成長の罠を説明する例としてはあまり適切ではないと思いますし、逆にこの2銘柄くらいしかちょうどいいサンプルがなかったとすれば、それはそれで説得力が欠けることになります。
セクター戦略の不都合な事実
ジェレミー・シーゲル教授が提唱するリターン補完戦略として、最も有名といえるのがセクター戦略でしょう。
具体的には、過去のリターンが優秀で、今後も長期的に利益を稼ぐことが見込まれる生活必需品セクター・ヘルスケアセクターの比率を高めるのが基本となっています。
赤本では、米国市場における1957~2003年の実質セクター・リターンについて以下のように記載されています。
| セクター | リターン |
| 金融 | 10.58% |
| 情報技術 | 11.39% |
| ヘルスケア | 14.19% |
| 一般消費財 | 11.09% |
| 生活必需品 | 13.36% |
| 資本財 | 10.22% |
| エネルギー | 11.32% |
| 電気通信 | 9.63% |
| 素材 | 8.18% |
| 公共事業 | 9.52% |
| S&P500 | 10.85% |
参考文献「株式投資の未来」
こうして並べると、生活必需品とヘルスケアの高リターンが際立ちます。
市場平均(S&P500)に対して3%前後の超過リターンを叩き出したことになります。
しかしここで注目してほしいのは、3番目にリターンがいいのは情報技術であるという点です。
これは、赤本全体の結論から考えるとちょっとモヤモヤする事実ではないでしょうか?
シーゲル教授はハイテク株やIPO株に対しては懐疑的な見方をしており、現在でもその傾向は変わっていないように感じます。
しかし、情報技術と言えばまさにその成長の罠という概念から真っ向からぶつかるようなキラキラセクターです。
それに対する弁解(言い訳?)として、赤本では以下のように語られています。
結果的に、ハイテク・セクターの運用は、S&P500種平均にかろうじて届く程度でしかない。1957年から1960代前半にIBMが飛び抜けた成績を残していなければ、平均を下回っていたであろう。この時期、IBMはコンピューター市場を独占していた。
出典「株式投資の未来」
IBMという特定の1銘柄(しかもセクター最大級)を例外のように扱うのは、他セクターのリターンにも同様の理由があると推測することができてしまうので、つみ次郎としてはあまり納得できない理屈です。
上記の文章だけでも苦しいですが、前述したとおりIBMは赤本の中では冴えない不発弾扱いされている銘柄ですので、ここで急に持ち上げられているのは尚更違和感があります(笑)
成長の罠の話とまとめると、情報技術セクターもIBMも市場平均に勝っているという不都合な事実が浮かび上がることになります。
未来の株式の買い手
ここからは少しテーマを変えて、株式ではなく投資家に関する内容に触れていきます。
つみ次郎はかなり楽観的に考えている部分なのであまりブログでも考察したことはありませんが、私たちが今積立している株を将来誰に売るか?という話です。
日本の場合、現在進行形で少子高齢化が進んでおり、今株をしこたま持っているジジババは売って換金しますが、買い手となりうる若手は人口も少なく、給料も少ないので株を買っている余裕はありません(一部を除く)
売りたい人>買いたい人になれば神の見えざる手により株価は下落するため、特に私たちの世代にとっては大きな問題と言えます。
それに対する答えとして、第15章「世界的解決ー真のニューエコノミー」では、以下のようにまとめられています。
退職者が必要とするモノを、だれがつくるのか?退職後に売却する資産を、だれが買うのか?本章で、答えがあきらかになる。モノをつくるのは途上国の労働者であり、資産を買うのは、途上国の投資家だ。高齢化する世界の人々は、必要なモノとサービスを輸入し、代金を支払うために、手元の株式と債券を途上国の投資家に売却する。
出典「株式投資の未来」
とても心強い答えですね。
日本では人口が減少していますが、世界的に見れば人口は増えていますし、人間の欲望を原動力とする資本主義が発展し続けることで新興国も先進国並みの経済力を手にすることになるでしょう。
先進国と新興国の差がなくなっていくという事でもありますけどね
つみ次郎が積立している投信やETFも、間接的に新興国の人たちに渡っていくことになります。
世代や国境を越えた、資本主義のバトンタッチと言えます(今年一番のドヤ顔)
しかしそれを実現するためには、世界規模の経済発展はもちろん、世界中でヒト・モノ・カネが自由に行き来できる世の中を作らなければなりません。
ですが、貿易摩擦・移民問題…そして多国籍企業の税金逃れ等を考えると、真のグローバリゼーションには程遠い状況です。
また経済の中心が先進国から新興国にシフトした時、これまで米国主導で行われたきた株主最優先の資本主義経済が維持されるかどうかも大きな問題です。
とはいえ、上記問題の多くは人口増加が解決してくれると思いますし、通貨発行権を持つ米国が金融の中心に居続けるは思いますので、つみ次郎としては前述したとおりそこまで心配している部分ではありません。
日本株だって外国人投資家の影響が大きいですし、米国株ならば尚更買い手に困ることはないでしょう。
読みやすさと独自の考察がウリ
久しぶりに読みましたが、赤本はそこまで内容が複雑ではないので非常に読みやすいですね。
本記事では全体的に批判側の立場で書評を書いてみましたが、全体を通せば分かりやすい例や文章が多いので投資初心者でも理解しやすいのではと思います。
同じくシーゲル教授の著書である「株式投資第4版(通称:緑本)」はやや難しい内容に感じるので対照的です。
データだけでなく、シーゲル教授自身の考察・解釈が強く反映されているのも、緑本に対する赤本の大きな違いと言えます。
その意味では、本記事のようにツッコミポイント(?)を見つけていくのも面白い読み方であり、初心者から上級者まで広くおすすめできる1冊なのではないかと思います。
![]()
![]()
![]()
ブログ村ランキング
シーゲル二郎